投稿日:2022年10月05日 00:26 文字数:16,958
転生したらボブゲーの主役になっていた件【イベント:ラッキースケベ!?】
お久しぶりです。転ボブ、ラッキースケベ編です。ちょっとだけえっちな表現があります。苦手な方は注意です
2ページ目:仁一
3ページ目:リュウカズ
4ページ目:クラカズ
5ページ目:ラスカズ
6ページ目:セフィカズ
となっています。好きなCPだけ見たい方はこちらを参考にしてください
三島一八。49歳。G社社長で父子家庭。
不幸にも事故に遭い前世の記憶を思い出した上、9人の攻略対象(全員男)のうちの誰かと恋愛関係にならなければ1年後に死を迎える宣告をされてから5ヶ月ほどが経過していた。
幸か不幸か攻略対象たちとの仲は安定しており、今のところバッドエンドに向かう様子はなさげだ、と午前4時の布団の中で考える。
「はぁ……」
それでもため息をついてしまうのはスマホの画面に映るサポートセンターが発信してきたメッセージのせいだった。
『本日8月1日は特別なイベントが開催予定となっています!何が起きるかはその場でのお楽しみ!!是非楽しんでくださいね♡』
いつも丁寧な口調をしているサポートセンターにしては砕けた文章。まるで別人が乗っ取ったかのようなその文面を見てカズヤはまたも大きなため息一つ。
「何が楽しめ、だ」
画面をタップしてメッセージを閉じ、会社を休むべきか否か考える。部屋に閉じこもれば変ちくりんなイベントに巻き込まれることはない──と言いたいところだがここ数ヶ月でイベント発生から逃れる術などないことは実感していた。寧ろ無理やり部屋の外へ連れ出されて厄介なことになるのは目に見えている。
「クソったれ」
結局、いつも通りの日常を過ごすのが一番だと結論を出したカズヤは起きる時間まで英気を養うため寝ることにした。
さて、今日は鬼が出るか蛇が出るか。
「父さん、起きてよ」
「んが……っ」
仁にユサユサと揺れ動かされ、ベッドの蓑虫となっていたカズヤは目を覚ました。カーテンから漏れ出す陽光はまだ弱いがこれから太陽が昇ればここにも強い陽光が入ってくるのだろう、と目を擦りながら仁の方を向く。
「今日はうまく朝食できたと思うから……ほら早く用意して」
「ああ……」
カズヤが起き上がると同時に部屋を出ていく仁。その背中を見送ってカズヤはぼんやりとした頭のままクローゼットへと向かった。今日は何曜日だ?と考えつつスーツを取り出し着ていく。ネクタイを結びワイシャツを着て、とそこまでいったところでそういえば今日は猛暑日になると昨日ニュースで聞いたことを思い出した。ジャケットをハンガーにかけたままにして手早くネクタイも外す。それから洗面所で顔を洗い歯磨きをすれば、鏡に厳めしい男の顔が不機嫌そうに映っていた。
(こんな顔の男に惚れるか普通?)
神々の遊び(?)に巻き込まれたとはいえ攻略対象たちが何故自分に惚れたのかさっぱりわからない。そもそも自分のどこに惹かれたのか。見た目は当然、仕事だって世間を見渡せばカズヤよりできる人間の方が多いだろう。性格も人付き合いの悪い自分は他人から好かれるタイプではないことは自覚している。それなのに彼らは何故か自分を好きになったのだ。
(哀れといえば、哀れだ)
自嘲気味に笑い、しかしすぐに表情を引き締める。どうせ考えたところで答えなど出ない。今はただ目の前に立ち塞がる攻略対象をいなしながら仕事をする。それだけだ。……そういえば朝から何か違和感がある。何か重要なことを忘れているような、いや今日変なイベントが起きることはわかっているが何か違和感が、と思案し始めたところでリビングの方から声がかかった。
「父さんご飯冷めるよー!」
「今行く!」
仁の声に急いで返事をして洗面所を出る。そのままリビングへ足を運ぶとテーブルの上には既に料理が置かれていた。目玉焼きやソーセージといった定番のものに加えてサラダも用意されているあたり、今日の朝食は随分と力が入っているらしい。
「ほう、一人でここまで作れるようになったか」
「まあね」
得意げに笑う息子を見ながら席に着き、いただきます、と二人で手を合わせて食べ始める。味は可もなく不可もない。仁が味音痴だった頃に比べれば天と地の差だ。
「今日も仕事遅くなるのか?」
「いや、特にそういうことはない」
「そっか……よかった」
この頃しきりに帰る時間を把握しようとしてくる息子、もとい攻略対象に戦々恐々としながら食事を進めていく。この様子ではいずれ自分が帰る時間を予測して職場の前で待ち伏せでもされそうな気がしてならない。そんなことを考えているうちに皿の上にあったものは全て胃の中へと消えていった。
「ごちそうさま。皿は水につけておくか?」
「ああ皿は俺が片付けるから父さんは仕事の支度してよ。遅刻したらまずいだろ」
「いや、皿を運ぶくらいやらせろ」
そう言って皿を流し場に運び支度をしようと足を一歩踏み出した瞬間、ツルッと足元が滑らかな音を立て、体が宙に投げ出された。
「うわっ!?」
「父さんっ!!」
仁がこちらに向かってくる。その速度はコンマ数秒、どころか瞬き一回分ほどの時間しかないだろう。どこからその速度を出せたんだと突っ込む余裕もなく体は重力に従って落ちた。このままだと確実に頭をぶつける。そう思い受け身の体勢を取ると。
「あっ!!」
仁が滑った。自分が滑ったところと同じ場所で見事にツルッと。しかもこちらに倒れ込んでくる形で。それに動揺してしまい体を捻ることも忘れてカズヤは仁の下敷きになった。
「ぐえッ……」
潰れた蛙のような声をあげたのはカズヤだ。息子の全体重を受け止めてしまったことで内臓が圧迫されたような感覚に陥る。幸いなことに頭は打っていないが、視界がやたら暗い。そうか目を瞑っていたからかとパチリ、目を開けるとそこには異様な光景が広がっていた。
「んむっ……何、これ、父さん」
「なっ……なっ……!」
何だこれ、という言葉は出てこなかった。出る余裕もない。
何故なら自分の着ていたワイシャツが謎にはだけており、そこから露出した胸筋に仁の顔が埋められていたからだ。胸のあたりにダイビングするのはまだいい。だが、はだけたワイシャツは何だ。まさかボタンが取れて落ちたのか?そう思って視線を下げると何故かズボンまでずり落ちそうになっている。おい待てベルトはしっかり締めてきたはずだぞ!と混乱しているカズヤに対し、仁はまだ転んだときの衝撃から覚めていないのか目を瞑って顔を胸に埋めたまま動かない。それどころか胸筋に手を伸ばして感触を確かめるように揉み始めた。
「と、さん?」
ムニムニムニュムニュと筋肉質な胸を揉む仁をどかすため腕を動かそうとするが生憎下敷きにされているためそれもできない。
「……なにこれ、硬い」
「じ、何を……!」
「あれ、ここ……何かある」
「ひっ!」
胸の突起、それを仁の指先が撫でた途端背筋にゾクッとした寒気のようなものが走った。これは本格的にまずい。バッドエンド一直線だ。そう判断すれば行動は早くなる。
「仁!!!」
唯一動かせた足で腹を思い切り蹴り上げ、怯んでいる隙に息子を押し退けたカズヤはそのまま立ち上がって距離を取った。
「痛ッ!」
「それはこっちの台詞だ馬鹿が!」
起き上がり服を整えながら怒鳴ると仁もようやく状況を理解できたのか顔を真っ赤にして頬に手を当てた。
「あれ……父さん……?って、ごめん父さん!!」
「何故俺の胸を触った!!」
「いや、柔らかいものが急に現れたからつい……」
「どんな言い訳だ!」
思わず突っ込みを入れるが、仁はというとまだ顔が赤い。そんなに恥ずかしかったかと思う反面、自分の息子がこんなにも変態だったのかとショックを受ける。いやここ5ヶ月で息子の癖はわかっていたはずなのにまだまだ把握しなくてはいけないことが多いようだ。
「とにかくだ!人の胸を許可なく触るのは駄目だ!!わかったか!?」
「ご、ごめんなさい……」
俯く仁にこれ以上怒れば本気で落ち込むか変な行動に出るかもしれないという危険信号が働き、カズヤは大きく息を吐いて怒りを抑える。
「次から気をつけるんだな。俺はもう行く。戸締まりはちゃんとしておけ」
「うん……」
自室でワイシャツを手早く取り替え荷物を持って玄関に向かう。靴を履いていると背後から声をかけられた。
「父さん」
「なんだ?」
「本当にごめん。あと行ってらっしゃい」
「ああ、行ってくる」
家を出てスマホを確認する。これもイベントの一つだと通知が来ているのだろう、と思いきやとんでもない文言が表示されていた。
『本日はラッキースケベデー!攻略対象との関係値が大きく変動する大チャンス!ハプニングが多発するので要注意!!※なお期間中好感度と危険度は見えませんがバッドエンドにいくことはないのでご安心を』
「……ふざけた真似を!」
要するに先程のハプニングも“そういうこと”なのだろう。洗面所で感じた違和感はいつも見えていた好感度と危険度が見えなかったことを指していたのだ。
苛立ちを抑えつつ通知をタップして詳細を見れば攻略対象限定でランダムに発生するとのこと。頭を抱えるしかない。今までのイベントにここまで大きな展開はなかった。死にかけたことやバッドエンドに行きかけたことはあるが。しかしよくよく思えばこのよくわからない恋愛事情も5ヶ月経っているのだ。そろそろテコ入れの時期だと主催者側が提案したのかもしれない。不幸中の幸いはバッドエンドに行くことはないというところか。
だがそれでも一つだけ言えることはある。
「セクハラというものをわかっていないのかこいつは……」
先程から何一つ応えてくれないサポートセンターに文句を言いつつ、カズヤは会社への道を歩き出した。そうしてこんな時に限って愛車は車検に出しているのだ。
昔は横に縦に振動していた電車も技術の進歩か静かに走るようになった。そのおかげか通勤ラッシュでかなりぎゅうぎゅう詰めの電車内でも酔うことなく立ち続けられる。とは言っても珍しいことに押しくら饅頭状態の車内はやはり気分の良いものではない。特に朝は。
そう思いながらもカズヤは何とかドア付近のスペースを確保する。次の駅でそれなりの人数が降りるだろうから、そこまでの辛抱だ。
(ラッキースケベ、ラッキースケベ……か)
そのような言葉自体先程のメッセージが来るまで知らなかった。調べるとどうやら本人に全くそんな意思はないにもかかわらず、意図せず性的な出来事に巻き込まれてしまうことのようだ。確かに仁が胸筋に触れてきた時は驚いたがあれもラッキースケベと考えれば納得する。せざるを得ない。
(誰かと今日会う予定は……ない)
仁を除いた攻略対象たちに会う予定はスケジュールにないが、ラッキースケベデーなんてメッセージが宣うものだからもしや強制的にでも接触させてくるのではないか、戦々恐々とする。今日はなるべく早く帰ろうと決意していると次の駅に着いた。反対側の扉が開き、一気に人が降りていく。と同時に人がどんどん入ってきた。
(こんな日に限って人が多い……!)
何か大きなイベントでもあるのか、今日に限って電車内は大勢の人間で鮨詰め状態になる。思わず舌打ちをしたくなるが我慢して降りる駅に到着するまでひたすら無心で待つことを決意した。そうして電車が発車し、少し落ち着いた頃。
「……?」
腰、いや尻に何かが当たるような感覚がした。最初は鞄かと思ったがそれにしては大きいし、何よりも体温がある。
(これは、……まさか)
急いで後ろを振り返ろうとすれば、突然電車がガタン!と大きな音を立てて揺れた。それと同時に身体がバランスを崩し扉に押し付けられる。尻に触れていた体温も更にギュッと押し付けられた。
「っ!」
「え、カズ、ヤ?」
「は?」
押し付けられた体温に息を呑むと聞き覚えのある男の声が後方から聞こえた。
「す、すまない。いつの間にか手がお前の尻に……」
「……リュウか」
振り返るまでもなくその声の主はリュウだ。どうやら押しくら饅頭状態のせいで意図しないうちに手をカズヤの尻に押し付けてしまったらしい。本日何回目かもわからないため息をつくが同時にこれでこいつのラッキースケベは終わりだなと安心した。
「とりあえず手を退けろ。不愉快だ」
「悪い、すぐに離……」
ガタン!とまたもや車体が大きく揺れ、今度はリュウが体勢を崩した。そのままカズヤに密着するように体が押し付けられ、手も離れることなくむしろ先程より強く掴まれる。
「おい、いい加減にしろ」
「本当にすまな、い」
「早く退けろ」
「すまん、身動きが今……」
どうやら今度はリュウの方が身動きを一切取れなくなってしまったようだ。満員の車内で無理に動こうとすれば当然他の乗客に迷惑がかかるだろう。仕方なく次の駅に着くまでそのままの状態を保とうと諦めた。
「……」
だがそこで気付いた。いや気づきたくなかった。リュウに押し付けられているのは手だけじゃない、……腰も押し付けられている。更に電車の振動のせいでまるで性行為における立ちバックをしているかのようにユサユサと押し付けられているのだ。
「リ、リュウ……」
決して痴漢などではない。何もかも満員電車で起こったハプニング、偶然なのだ。しかしラッキースケベデーという恐ろしい概念を植え付けられたカズヤにはこの状況は非常にまずかった。
(腰を押し付けないでくれ……頼む……)
公共の場でイケないことをしているという背徳感がカズヤを襲い、身体中が熱くなってくる。よく見ればリュウもリュウでカズヤの背中に顔を押し付けているのだからこの状況のおかしさに気づいているだろう。お互い身体中に熱を持ちながら居心地の悪い思いをしているとやっと次の駅に到着した。乗客が何人か降りていき、やっと身動きがとれるようになる。
「……ふぅ」
安堵のため息をつき、体を反転させるとそこには顔を真っ赤にしたリュウが置き場のない手を彷徨わせていた。
「その、悪かっ……」
「貴様も俺も悪くない。不可抗力だ。ただ一つだけ言っておくことがある」
「な、なんだ?」
「今後一切このことについて話すのも触れるのも禁止する。わかったか?」
「……わかった」
何だかそんなばつの悪い顔をされ心から謝られると怒るのも馬鹿らしくなり、そのまま黙ることにした。リュウも戸惑ってはいるが納得したのか黙ってくれる。約束は守る男だから今回のことは秘密にしてくれるだろうがこのラッキースケベがどんな好感度変動を起こすのか、なんて考えただけで頭が痛くなってきた。
朝から続いたラッキースケベも社内に攻略対象がいなければ何も起きやしない。むしろバッドエンドに行くことがないとわかれば心も安定してくるものだ。それどころかスムーズに業務ができたおかげで午後の仕事も滞りなく進められるようになった。が、やはり人生そううまく進められるものではないらしい。
「悪い。社長からすぐに行けと言われたもんで」
「……構わん。で、用件は何だ?」
「この資料に書いてあることについてなんだが……」
昼休みが終わり午後の仕事に取り掛かろうとした直後、突然プレジデント・神羅から連絡が入った。曰くある取引の確認のためそっちに社員を送る、対応してくれ、と何とも急いでいるような口調だった。本来ならメールで済ませるところをわざわざ電話でかけてきたということはそれだけ急ぎだということだろう。幸い今日は取引先との会議もないので、すぐに了承した。この時点で察すべきだった、とは後の反省点だ。
そしてやってきた人物は攻略対象たるクラウドであった。仏頂面もツンと立つ金髪も相変わらずで逆に安心する。
「それで……これが……」
淡々と仕事内容を確認する姿は事情がなければこちらが引き抜きたいほどクラウドは真面目で誠実だ。そうして話を進めていくと確認すべき資料が資料室にあることが判明した。
「資料を取ってくる。貴様もついてこい」
「え、でも俺は……」
「少しばかり重要な資料だ。資料室からそう持ち出せないものだが貴様にも見せておかんとな。ここの代表たる俺が許可したから問題ない。尤も、貴様が不正に資料を見る隙なぞ与えんが」
「……わかった」
クラウドを連れ執務室を出てやって来た資料室。人の出入りが少ない場所であり、埃っぽい臭いが充満していた。目当ての資料は確か一番上の棚にある。180cmあるカズヤでも背伸びをしないと届かない場所だ。170cm台のクラウドも当然届きやしない。
仕方がないとため息をつき、つま先をピンと伸ばして腕を伸ばす。……ファイルは随分奥の方にあるようで、もう少しだけ背を伸ばさねばいけなかった。
「大丈夫かカズヤ?」
「問題、ない」
「脚立は……ここにないのか」
残念なことにここには脚立はないので思いっ切り背を伸ばし手を伸ばす。限界まで足と手を伸ばしたところでやっとファイルに手が届いたその瞬間。ツン、と攣る感覚が足全体に走った。所謂こむら返り。慌てて脚を引っ込めようとしたがそれがいけなかった。足のコントロールがきかず、クラウドのいる後方へ倒れ込んでしまった。
「ぐ、ぁっ!」
「うわっ!」
手に引っ張られた大量の資料と共にドサッ!と大きな音を立てて2人は倒れた。バサバサッと降ってくる資料は痛かったが、どうやら咄嵯に庇うようにクラウドが下敷きになってくれたらしくそちらの方では痛みを感じなかった。感じなかったのだが。
「…………」
「…………んぅっ!」
ラッキースケベデーに油断は大敵。クラウドに覆いかぶさる形になったのは位置の都合上仕方ない。だがその覆いかぶさり方が問題だ。
クラウドの顔面、そこにカズヤの尻を押し付けているような形になっているのだ。顔面騎乗とはまさにこのこと。付け加えればカズヤの股間あたりがちょうどクラウドの鼻先に当たっていた。布越しとはいえダイレクトに伝わる匂いと温もり、更に騎乗されているせいで呼吸が苦しくなっているクラウドが不本意ではあろうが息を激しくしている。
「すまん、すぐに避け……ッ!」
避けるため足を動かそうとするが攣っていたことを忘れていたせいで変に動いてしまった。
「あっ!ぐぁ……」
「ンンッ!ンー!!」
結果としてクラウドの顔面に更に尻をグリグリと押し付けてしまい、かえって逆効果となってしまった。クラウドの荒くなっていく息が布越しの股間にかかるたび、変な気持ちになってしまいそうになる。
「クラウド……少し動くぞ。我慢してくれ」
幸いだったのは腕が動けたことだ。腕の力だけでズリズリと体を動かし、尻をクラウドの腹のあたりまで持っていくことに成功した。
「はぁ、はぁ、はぁ……」
やっと新鮮な酸素を取り込めたクラウドが荒い呼吸を繰り返す。振り返るとその顔には涙の跡があった。男の体重がかかった尻を押し付けられれば誰だってそうなるだろう。申し訳なさでいっぱいになりながらカズヤが立ち上がろうとしたその時、クラウドの腕がカズヤの足首に伸びた。
「!? クラウド、何を」
「足、大丈夫か?ええっと……立てないならマッサージしてやる」
「は?」
「靴と靴下、脱がすぞ」
答える間もなく靴下と靴がスポンと抜けていく。晒されたのは綺麗なんて言えやしない、少し傷だらけの足裏だ。
「土踏まずのあたりが痛いのか?」
「あ、ああ……」
「他に痛むところは」
「……大丈夫だ」
妙に優しい声色で話しかけられ戸惑ってしまう。クラウドはカズヤの返事を聞くと優しく丁寧にを揉みほぐしてくれた。土踏まずから足指の付け根、踵まで解されればやっと足の攣りが治ってくる。
「クラウド、もういい。治ってきた」
「そうか」
ようやく立ち上がるとクラウドも立ち上がり、乱れてしまった資料を整え始めた。カズヤも手伝い、整えたところで改めてクラウドに謝罪する。
「悪かった。まさかこむら返りを起こすなんてな……怪我はないか」
「俺は平気だ。アンタは」
「問題ない。さっさとここから出るぞ」
そう言って歩き出そうとしたところでグイッと肩を掴まれ振り返らせられる。何事かと思えば目の前一杯にクラウドの顔面があって胸がドキリと跳ね上がった。
「何を」
「靴と靴下、忘れている」
「あ」
クラウドに脱がされたそれらは乱雑に散らばって床に落ちていた。
そんなこんなで今日の業務が終わった。もう少し残って仕事を処理してもよかったが、秘書から顔色が悪いわねと言われるものだから大人しく帰ることにする。確かにラッキースケベの嵐で顔色が悪くなっていたかもしれない。
寄り道は禁物だ。繁華街の方にはテリーやポールがいるだろう。このラッキースケベデーなる日に出会ったら一発ラッキースケベをかますことは間違いない。そうして繁華街の端をサッサと歩き足早に家路へ。
「カズヤか?」
不意に後ろから聞き覚えのある声をかけられギギギと嫌な予感を滲ませながら振り向くとそこにいたのは異母弟、ラースだ。三島財閥のやたらメカニカルな仕事着ではなくラフなシャツとチノパンでカジュアルに決めている。普段のキリッとした表情とは違い、柔和な雰囲気を醸し出していた。
「……なんだ、貴様か」
「なんだとはご挨拶だな。いつもなら堂々と歩いているアンタが端をコソコソ歩いているもんだから思わず声をかけたんだ。やましいことでもしたのか?」
「誰がやましいことなんてするか。寧ろ貴様が……」
そこまで言って口を閉ざす。とにかく会話している場合じゃないのだ。早いとこ帰って風呂に入って寝てこのラッキースケベデーを終わらせたい。そう思い立ち去ろうとするとまた呼び止められる。
「待てよ。せっかく会ったんだ、飯でもどうだ」
「断る」
「そう言うな。奢るから」
「断る。仁が飯を作って待っているからな」
「……また仁のこと、か」
ラースの表情が曇りがかる。その「仁のこと」に籠められた感情など、大方嫉妬か何かだろう。しかし今のカズヤにはそれどころではない。一刻も早く帰りたいという気持ちが先走ってしまっている。それがまたラッキースケベを呼ぶとは知らずに。
歩みを進めようとした瞬間、昼間と同じように足がピン、と攣りその場にしゃがみ込んでしまう。昼間の後遺症か尻餅もついてしまい完全に動けなくなってしまった。
「い、ッ……」
「大丈夫か!?」
ラースが肩を貸そうと駆け寄ってくる。その手を払い除けようとするが、足が動かずそのまま腕を取られてしまう。
「俺に触るな!」
「怪我人に言われても困る」
そうしてカズヤは半ば引きずられるようにして近くにあったベンチに座らせられた。ラースは「ちょっと待っていろ」と言うと道の向かいにあったコンビニに駆け込んでいく。
何というかラッキースケベだけでなく不幸にもなっているのではないだろうかとネガティブに考えてしまう。朝は胸を触られ腰を押し付けられ、昼は顔面騎乗をかましてしまうなんてラッキースケベというより不幸な事故だ。そう考え俯いているといつの間にかラースがこちらに戻ってきていた。手には膨らんだコンビニの袋がある。
「足はどうだ、捻挫か?」
「いや……攣っただけだ」
「さっき盛大に尻餅ついたから攣った上に捻挫している可能性もあるぞ。ほら、足を出してくれ」
ラースが隣に座り、袋から包帯やらテーピングテープ、湿布を出してテキパキとカズヤの足に処置を施していく。三島財閥の実戦部隊にいる彼らしく、手際よく処置を終えた。ひんやりとした感触に小さく息を漏らすと、ラースが小さく笑っていた。
「なんだ」
「いや、アンタにも可愛いところあるよな。こういう感じで不意に出てくる」
「馬鹿にしているのか。……さっきは悪かった。礼を言う」
「気にしないでくれ。俺も不意に近づいて驚かせたしな。駄賃は素直なアンタが見れたからそれで充分だ」
「……ふん」
手当てを終えるとラースは一緒に買ってきたであろうミネラルウォーターを渡してきた。開けて数口、喉が潤う感覚で渇いていたのだと気づく。ああクソ、碌に水も飲めていなかったのかと実感して衝動的に残りのミネラルウォーターを頭からジャブジャブと被った。
「何しているんだカズヤ!?」
「……苛立っただけだ。気にするな」
「いや気にするだろ。ほらハンカチ」
差し出されたハンカチを受け取り顔と髪の水分を拭う。ダレッと垂れてきた髪は面倒で下ろしたままにしておき、シャツの裾で顔をゴシゴシと擦るとラースが苦笑いしていた。
「随分ワイルドだな」
「フン。俺は昔からこうだ」
「確かにそうだったかもな。まぁ、い……」
そこでラースの言葉が途切れる。何かあったか?と顔を横に向けるとラースが赤面していた。その視線の先はカズヤの胸元、シャツに向けられている。
「……どこを見ている」
「え!?いや、その……」
「言え」
「不可抗力だ……」
「何を言っているんだ貴様」
「すまない、本当に申し訳ないと思っている。見えてしまったからその見ただけで……」
ゴニョゴニョと言葉を発するラースに怪しげな目を向ける。その目はどこか泳いでいて嘘をついているようには見えない。しかし、やはり胸が見えたのは本当のようだ。別に男の胸を見られたところで減るものでもないのだが。
「だから何が」
「シャツ……透けて、その……乳首が……」
「ちく、あ……」
着ているシャツの胸元を見ると、先程のミネラルウォーターで中が透けてしまっていて突起したピンク色の乳首がくっきりと浮かび上がっていた。そこが被った水によって少しだけ湿っており、先端がいつも以上にぷっくりと膨らんでいたのだ。それを認識した瞬間、カズヤの顔が一気に熱くなる。慌てて手で隠すが時すでに遅し。
「み、見るな!この変態!」
「す、すまなかった!!」
互いに顔を背け合うが、気まずい雰囲気が二人の間に流れる。なんとも言えない空気の中、先に口を開いたのはラースの方であった。
「その、悪かった。男の乳首に興奮するなんて自分でもどうかしていると思うんだがどうしても見てしまうというか、その、アンタの身体が綺麗というか……」
「もういい黙ってくれ」
「そうだよな、男にこんなこと言われても気持ち悪いだけだよな。悪い……」
うるさい貴様が俺を性的に見ているのは知っているんだぞと声を大にして言えばこいつはどんな反応をするだろうか。きっと、そんなことはないと否定してくるだろうがラースのことだから最終的に認めてしまうだろう。そういう男で、弟なのだ。
「応急処置をしてくれた分で今回の件は許してやる。なんなら見るか?」
「ばッッ……!何言っているんだアンタは!!」
「冗談だ。次はないと思え」
そう言って立ち上がると、カズヤはベンチに座らせたままのラースを置いて歩き出す。背後から聞こえる「待て!」という制止の声を無視してカズヤはそのまま家路に向かうのだった。
そろそろ家に到着する。やっと解放された気分になり足取り軽やかに道を進んでいくと後方に気配を感じ振り返る。と、闇夜の中でギラリと金属が光った。その光の持ち主は全身黒ずくめでフードを深くかぶっているため顔は分からない。しかし、その手に握られているのは明らかにナイフだ。すぐ自分を狙っているのだと分かった。
「……貴様は誰だ?」
問いかけるも返事は返って来ず、代わりに黒ずくめがこちらに刃を向けて突進してくる。あからさまに素人の動きだ。横に避け脇腹に一発蹴りを入れればあっさりと蹲ってナイフを落とし悶絶してしまう。その隙に腕を捻り上げて地面に組み伏せた。
「三島財閥にしろ何にしろ、警察行きだ。ここの近くに交番があることをわかっている上での犯行か?」
「クソッ……!!」
抵抗しようともがく黒ずくめの腕を捻り、鞄にしまっていた適当な紐で後ろ手に結ぶ。そのまま引き摺るように交番に行けば、黒ずくめは最近ここら辺で目撃情報があった不審者ということが判明。警官から簡単な事情聴取をされ終わって帰ろうとしたそのとき、聞き覚えのある声が入口から聞こえてきた。
「こちら落ちていましたので……お届けします」
「ありがとうございます」
「いえ。……ん?」
「……チッ」
そこにいたのは相変わらず長い銀髪を靡かせた男、セフィロスだ。夏らしくクールビズスタイルで、それが似合っているのがらしいといえばらしい。攻略対象一番の危険人物が何故ここにいるのかわからないが、とりあえず軽く挨拶を交わして足早に帰れば何も起きないはずだ。そう思いその場から立ち去ろうとすると、呼び止められる。
「おい」
「……なんだ」
「何かあったのか?」
「不審者に襲われたから事情聴取されただけだ」
「襲われた!?怪我はないのか!?犯人はどこにいる!!今すぐ殺して」
「俺が捕まえた。そうなんで物騒なんだ貴様は……」
「そうか。それはよかった。流石カズヤだな」
「ナチュラルに上から目線で俺を評価するな」
どうせ何を言っても聞かないだろうと諦める。それよりも早く帰りたいのだが、警官がお知り合いの方がいるなら一緒に帰った方がよろしいかと思いますよ、と正確無比で今はいらないアドバイスをくれたおかげでセフィロスと一緒に帰る手筈が出来上がってしまった。セフィロスは警官の言葉にわかりました、では私が責任を持って……と美しい営業スマイルで答え、サラッとカズヤの隣に立った。
「さあ、行こうかカズヤ」
「……ああ」
夜道でセフィロスと2人きり、なんて安心できるものかと心で毒づきながら帰路につく。セフィロスはナチュラルに車道側を歩き、カズヤに歩幅を合わせてくれているようだ。それが何だか悔しいような何やら。
「今日も暑かったな。水分補給を怠ると危ない。あと日焼け止めも塗った方がいいだろう。日に焼けたら大変だろう?何なら私が使っている日焼け止めを貸してやるか」
「1人で勝手にべらべら話を進めるなこの利口馬鹿!塞がないと死ぬ病気なのか貴様!」
「酷い言い草だな。私はただお前の身を案じているというのに」
「案じるにもほどがある。こういうのは余計なお世話というんだ」
そうやっていつも通りの他愛もない喧嘩をしながら歩いていくが、時折セフィロスが顔を見つめてくる。その視線に気づかぬふりをして歩みを進めるが、やはり見つめられる時間は増えていくばかりだ。
「……本当に大丈夫か。さっきの通り魔事件もそうだが今日はおかしいぞ。心配事でもあるんじゃないのか」
「しつこい。何も無いと言っているだろう。貴様が気にすることじゃ」
「私はお前を誰より守りたいと思っていて、大事にしているつもりだ。だからこそこうして……」
「黙れ」
「……すまない。だが、これだけは言わせてくれないか。私はどんなことがあってもお前の味方だ。たまには頼ってくれないか?」
「…………」
言葉が詰まる。どうしてそんなことをこんなときに。はぁ、と本日何回目かもわからぬため息をつきセフィロスの方を見る。と、先程まで余裕のあった顔は悲しげに歪んでいた。
「……別に今日色々とハプニングがあってな、頭が混乱しているだけだ。さっきの通り魔だけじゃなくて朝から変なことばかり続いている。少し疲れて思考回路が鈍っているんだろう」
「……そう、か……。すまなかったな。無理をさせてしまって」
「貴様に謝られても気持ち悪い。が、まあ……」
「まあ?」
正直なところ先程の言葉は胸に滲みたというか何というか、少しばかり嬉しかったのだ。だからこれは感謝のつもりで言っただけで他意はない。ないのだ。
「……ありがとう」
「…………!!」
「く、間抜け面め」
悲しげに歪んでいたセフィロスの顔が一気に明るくなりこちらに抱き着こうとするが腕力で断固阻止する。流石に往来でそれは恥ずかしすぎるので断固拒否の姿勢を見せたが、セフィロスは不満げだ。
「照れることはないのに」
「うるさい。早く行くぞ」
「ああ、そうしよう。カズヤが無事で良かった。やっと安心できる」
肩をすくめて帰路を急ぐ。マンションまであと数百m。このまま互いに何も起きずに帰れればいいのだが──カズヤは先程の通り魔未遂事件ですっかり忘れていた。今日はラッキースケベデーで、そしてここは比較的光の少ないのない夜道だということを。
「じゃあここまでだ。カズヤ、寄り道なんかするなよ」
「誰がするか。早く行け」
「ああ。じゃあまた……」
夜、特に光の少ない道は足元に気をつけろというのは常識中の常識だ。だがその常識がラッキースケベに通じるわけもなく──
「あっ」
セフィロスが足元に落ちていたゴミ袋を踏んでバランスを崩した。咄嵯にカズヤが手を伸ばすが間に合わず、ぐりんとセフィロスが一回転したかと思うとカズヤに覆いかぶさって───
「うわっ!?」
「!?」
カズヤを壁に押し付けしゃがませるような形で倒れた。所謂座り壁ドンというべきものだろうか。衝撃のせいで意識が半ばどこかに飛んでいたセフィロスだったが、左手を動かすと柔らかいボールと棒のようなものに触れた感触があった。右手もこれまた柔らかい、しかし一箇所だけ突起のようなものがある壁に押し付けられている。
何だこれは、と好奇心のまま両手を動かしてみると、ひぁッ、と小さく高い声が聞こえた。何だかとても心地好い気がして、そのまま両手を動かし続ける。すると今度は、やんっ、と甘い吐息が漏れてきた。
(なんだこれは、不思議だな)
夢中になってその2つの何かを弄り続けるとそのうち明確に艶やかな喘ぎ声が確かに聞こえてきた。
「せふぃ、きさッ、あぅ……や、そこ、やめ、あッ!」
「?すまない、よく聞き取れなかっ、た」
艷やかな声が聞こえたおかげかやっと意識が明確に戻ってくる。そうしてセフィロスが目を開けると。
「え」
そこには顔を真っ赤にして涙を浮かべているカズヤがいた。その瞳は潤み、顔も赤く染まっている。そして何よりセフィロスの手があった場所は──
「な、どうしてこことここにッ、ピンポイントで手を入れられるんだこの……変態ッ!!」
カズヤのシャツの中と、ズボンの中であった。しかも見事胸と股座を掴んでいる。ようやく自分が何をしてしまったのかを理解し、サーッと血の気の引く音が聞こえるような感覚を覚えた。
「す、すまない!!いつの間にか手がここに」
「それなら何故俺の身体をまさぐる必要があった!?」
「あ、いやその、無意識に、……手が動いていた」
「ふ、ふざけやがって!もういいからさっさと退け!!」
「わかった」
そうしてセフィロスが手をカズヤの体から素早く抜いた。それがまあいけなかったのだろう。結果として胸と性器を擦るような形になってしまった。
「ぁ、んぅッ……!!」
今までセフィロスが聞いてきた嬌声で一番艶のある声。びくんと大きく震えたかと思うと、次の瞬間には力が抜けたようにぐったりとしてセフィロスにもたれかかった。
「カ、カズヤ?」
恐る恐る名前を呼ぶが返事がない。どうしたものかとその顔を覗き込むと、先程以上に目を潤ませ、顔を真っ赤にして口の端から無意識に涎を垂らしている姿が見える。これはもう、そういうことだと察してしまった。
「……っ、あ、う」
「……カズヤ、その」
「…………このッ!!変態、助平、色情狂、発情期野郎が!!!」
光の少ない夜道にパァンと小気味良い音と罵声が響き渡った。
セフィロスから逃れるように家に入り、玄関の鍵をかける。勢いでドアチェーンもつけるとリビングにいた仁が驚いた声を上げて駆け寄ってきた。
「どうしたの父さん?あっ……いや朝の件は本当に」
「違う。不審なやつが帰り道にいたから念の為にかけただけだ」
「そっか……」
今朝の出来事は事故であり不可抗力だ。それはわかっているし、今は考えれば仁が起こしたラッキースケベなど優しいものだった。最後の最後で食らったラッキースケベがあまりにも強烈すぎたのだ。男の尊厳もクソもないほどに辱められた気分になり、思い出しただけでぶるりと体が震える。まさかあれだけのことをされて何も思わない男がいるはずないのだ。だがそれを口に出せば仁に要らぬ心配をかけてしまうどころか仁がセフィロスのもとに突撃しかねない。
「すまん。少し1人にさせてくれ」
乱雑に靴を脱ぎ、足早に自室へと向かう。背後から困惑した仁の声が聞こえたが、構わず部屋に入るとそのままベッドへ倒れ込んだ。何も考えずに数分ボーッとして、ふとセフィロスの手が差し込まれた股座を確認するためズボンを捲くってみる。
「…………最悪だ」
パンツの中はしっかりと白濁液が付着している。ズボンの方まで染み込んでいないか確認すると幸いそこまでではないようだ。それよりもセフィロスの手で達してしまったという事実、何より自分の体がこんなにも敏感だったということの方がショックだった。
「あいつのせいで、俺は」
あんな奴で感じてしまった。その事実が何よりも悔しくて、恥ずかしい。体を弄られ、胸や揉まれ挙句の果てには性器を握られたというのに──勝手に気持ちよくなって達している。
そんな自分の体が一番嫌になった。
(いっそこれなら、あいつも前世を思い出せばいいのに)
そうすれば、きっとセフィロスを否定して、それで……なんて考え、ふとスマホを手に取った。そういえばこのイベントについてサポートセンターに聞かなくてはいけなかったことを思い出したからだ。早速アプリを開くとそこに映っていた文言にぎょっとする。
『譛ャ譌・縺ッ繝ゥ繝�く繝シ繧ケ繧ア繝吶ョ繝シ�∵判逡・蟇セ雎。縺ィ縺ョ髢「菫ょ、縺悟、ァ縺阪¥螟牙虚縺吶k螟ァ繝√Ε繝ウ繧ケ�√ワ繝励ル繝ウ繧ー縺悟、夂匱縺吶k縺ョ縺ァ隕∵ウィ諢擾シ�シ≫サ縺ェ縺頑悄髢謎クュ螂ス諢溷コヲ縺ィ蜊ア髯コ蠎ヲ縺ッ隕九∴縺セ縺帙s縺後ヰ繝�ラ繧ィ繝ウ繝峨↓縺�¥縺薙→縺ッ縺ェ縺��縺ァ縺泌ョ牙ソ�r』
ラッキースケベデーのお知らせは文字化けしていた。よく見ればアプリ全体の文章が文字化けして読めなくなっている。
「どういうことだ……サポートセンター!」
いつもならその名を呼べばすぐに応答してくれるはずのサポートセンターも何故か沈黙したままだ。何かあったのかと不安になっていれば不意に通知音が鳴り響いた。
「何だ一体!」
画面をタップするとそこには【緊急メンテナンス終了】の文字があった。一体何が起きたんだと首を傾げていると突然画面が切り替わり元あったアプリの画面が映し出される。
『こちらサポートセンターです。一八様、ご無事でしょうか』
「……ああ」
スピーカーから聞こえてきたサポートセンターの声にホッと胸を撫で下ろす。何だかいつも通りが戻ってきたようで安心する。
『大変申し訳ございませんでした。昨日より何者かによって管理権を乗っ取られてしまいまして……先程メンテナンスが完了しましたのでご安心ください』
「そう……ん?待て。じゃあ今日のラッキースケベデーは」
『ラ、ラッキースケベデー?それは一体どのような』
その口ぶりから察するにサポートセンターは今日あったラッキースケベの数々を把握していないらしい。つまり、このイベントを仕組んだのはサポートセンターではなく、アプリに介入してきた何者だということだ。
サポートセンターに今日あったことを話すと、彼女(?)も驚いたように声を上げた。
『そのようなことが…………悪魔め。次はしっかりとファイアウォールを用意して焼き尽くしてあげましょう』
「……まあ、できるならそうしてくれ。今日みたいなことは二度と御免だ」
『了解しました。お詫びとして本日変動した好感度及び危険度について微調整します。……とても高くなってますね』
サポートセンターが攻略対象たちの好感度・危険度を映し出すと仁、リュウ、クラウド、ラース、セフィロスの数値が軒並み上昇していた。特にセフィロスに至っては好感度危険度共々100に迫っている。
「うげ……」
自分らしくもないドン引きの声が出てしまった。元々の数値がアレとはいえ、流石にここまで来たらもう何も言えない。
『では一八様、本日は以上となります。お疲れ様でした。好感度・危険度の調整についてはおまかせください』
そうしてぷつり、と通話が切れた。とりあえずこれで今日の怪しげなイベントは終わったのだろう。しかしそれにしたって今日のイベントを巻き起こした黒幕は何を考えているのやら……と一息つけた途端、眠気が襲いかかってきた。晩ごはんを用意してくれた仁に申し訳ないと思いつつゆっくり瞼を閉じていく。
(ラッキースケベなぞ二度と御免被る)
そんなことを考えていればいつの間にか夢の中に落ちていた。窓の外から聞こえてきた聞き覚えのある笑い声、否、自分の笑い声は無視する。何となく、それが黒幕だとわかってしまったのだから。
笑い声の主は部屋の中のカズヤを一瞥すると蝙蝠のような羽を生やして半月に飛び立っていく。その姿はカズヤと瓜二つで、顔には歪んだ笑みを浮かべていた。
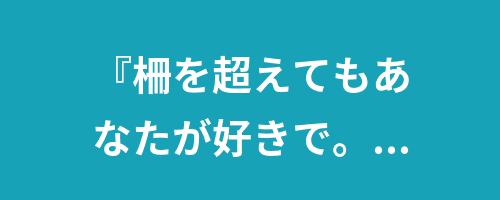 2025年04月06日 12:00〜翌11:50『柵を超えてもあなたが好きで。』クロスオーバーCPオンリークロスオーバーサークル参加受付期間0 / 72sp
2025年04月06日 12:00〜翌11:50『柵を超えてもあなたが好きで。』クロスオーバーCPオンリークロスオーバーサークル参加受付期間0 / 72sp
