投稿日:2022年05月27日 22:53 文字数:11,294
転生したらボブゲーの主役になっていた件【イベント編】
第二弾となります。
今回はクラカズ、テリカズ、ポルカズ、李一でイベントやってみました。
【クラウド√イベント】
クラウドが神羅カンパニーからG社に派遣されてきて数ヶ月。彼はすっかりこの会社に慣れ、時たま笑顔を見せるようになった。カズヤが彼を期間限定秘書として隣に置いたのは好感度を見張るためでもあるが、同時にちょっとした親心が働いたのは違いない。
一見クールに見えるクラウドだが実は少しばかり子どもっぽい上負けず嫌い。これは前世の記憶でわかっている。それに加えて知ったのは甘えん坊な一人っ子気質だということだ。わからないことがあるとむっと悩みつつも教えを請うてくる姿は成人男性にしては可愛らしいのではないだろうか。
尤も、攻略対象とあらば油断は禁物。そんな姿に絆されイベント発生からのバッドエンド直行なんてことになったら目も当てられない。
だから今日も好感度調整のため普通に接していた、はずだった。
「いつも思うけど、カズヤは鈍いよな」
油断、していた。ただ午前中行った他社との打ち合わせが滞って妙に疲れ、執務室の椅子でうたた寝をしていたのが悪かったのだろう。クラウドの声がやけに近く聞こえて意識が浮上したときにはもう遅かった。目を開けるとクラウドの顔がカズヤの顔数センチ手前まで迫っていたのだ。
「クラウド……!貴様ッ……」
慌てて離れようとするも寝起きの体じゃほとんど動けず、両の手首を掴まれ身動きが取れなくなる。
ズボンのポケットに仕舞われていたスマホがバイブレーションを鳴らす。イベント発生か……!と思ったときにはもう遅い。
「ズルいよなアンタ。本当に、ズルいよ」
「何がだ……!」
「セフィロスを鬱陶しがっているくせにいざ話すと楽しそうにしているし、仁の手作り弁当を食べるときは心底美味しそうに食べているし……」
「……」
「この間アンタと李超狼とポールの3人で一緒に飲みに行っているし、テリーだって、リュウだって……」
自信なさげに俯くその顔は、まるで捨てられた子犬のようだ。同時に好感度と危険度メーターがピコン、ピコンと静かに上がっている。ああクソ、こういうときに限って好感度が上がるイベントが起こるんだ。いやイベントに導かれているのは自分か……?と自問していると手首の拘束が解かれ、同時にふわりといい匂いが鼻腔をくすぐる。
あろうことかクラウドはカズヤの肩口に顔を近づけるとそのままそこに額を押し付けた。
「クラウド、離れろ」
「なあ、これは独り言だから聞き流してくれないか」
「……言ってみろ」
カズヤのその言葉を合図として、クラウドが声を紡ぐために息を呑んだ。
「例えば、アンタの周りにいる連中に嫉妬する人間がいる」
「ああ」
「その人間は実はアンタに恋をしているんだ。だからいじけて、つい構ってほしいような行動をとるんだ」
「……それで?」
「そいつは今、アンタの寝顔に見惚れてついキスをしたくなった」
「……」
「でもそれはダメだと自分に言い聞かせるんだ。もしそれをしたら、今まで必死に抑えてきた感情が爆発してしまうから」
「そしてそんな我慢をしても、こんなことをしてしまう、と」
「俺はきっと嫌われる。だけど本当はもっと近づきたい。触れられるようになりたいと願ってしまうんだ。それが俺なんだ。アンタが好きなんだよ……」
それっきり、クラウドは何も言わなかった。ただカズヤの首筋に熱い吐息がかかるだけ。好感度メーターは、止まらない。
カズヤの返事は……
【テリー√導入】
「疲れた……」
『お疲れさまでした』
心の底から出た言葉が繁華街の空気に消える。サポートセンターの無機質な声に答える気力すらなくなっていた。
数週間前に判明した新たな攻略対象、セフィロス(とクラウド)。家で待っている仁も相当厄介な好感度を抱えているがまさかそれ以上に面倒な相手とは思わなかった。いや前世のことを考えるなら当然と言えば当然の相手。想定しておくべき相手だったのだ。特にセフィロスに関しては。
だが現実は思うようにいかず。初対面であれだけの好感度と危険度、そして唐突に入ったイベントによりカズヤのメンタルは相当削れていた。正直なところ今から家に帰って仁の好感度メーターを見なくてはいけない……と思うだけで足取りが重くなる。
だからなのか。いつの間にか夜の公園にいた。ベンチに座ってぼんやりと夜空を眺めながらため息をつく。
「……サポート、残りの6人と出会えない可能性は」
『残り6人と出会えない可能性、1.2%。攻略対象である以上、ほぼ確実に貴方へと近づいてきます』
「……貴様、意外とはっきりしているな」
『全て事実ですので』
まあそうだろうなと納得し、また一つ大きなため息をついた。自分が恋愛ゲーム、それも男同士の恋愛、所謂BLというものの当事者になると誰が予想できただろうか。
手を目に当て、再び大きく深呼吸をする。これから自分はエンディングまでの一年間、好感度・危険度調整と仕事、家庭、その他諸々に対応しなければならないなんて。何足の草鞋、なんて笑えない。ストレスで胃が亡くなってしまう方が先なのではないだろうか。
「……とりあえず、帰るか」
どうせここで燻っていても変化などないのだ。よっこいせ、と重い腰を上げて帰路につこうとしたそのとき、トン、トンと何かが地面にぶつかり合うような音が後ろの方から聞こえてきた。
「ん……?」
振り向いた先にあったのは、ストリートバスケのコート。ジジジッ、と古い電灯が音を立てて点滅し、コート上にいる人間を照らしている。
コート上にいる人間は1人でフリースローをしていた。見ている限りでも10回以上連続で決めているのではないか。
「……あ」
普段なら目にも留めないその光景。だが今は不思議と目が離せなかった。その男がシュートを放つたび、リングに吸い込まれるようにボールが消えていく。ただそれだけのことなのに、心がすっきりとしていく。
気づいたときにはコートの近くまで歩み寄り、無意識のうちに呟いていた。
「……凄いな」
するとその声が聞こえたのかコート上にいた人物が振り返る。赤いキャップと赤いジャンパー、デニムジーンズ。それに束ねた長い金髪と宝石と見紛うほどの碧眼。
……いやコイツ、前世で見たことがあるぞ。
「おっ、見物客か。珍しいな」
間違いない、コイツはテリー・ボガードだ。爽やかな笑みも、その親しみやすさも、何もかもがカズヤの記憶にあるものと一致している。
「あ、ああ」
「最近よくここに来るんだが、こんな時間に人がいるのは初めてだよ」
「……そうなのか」
「おう!って言ってもこの時間帯しかできないんだけどな。色々バイト掛け持ちしているからさ!」
ハハッ、と爽やかに笑う姿は前世の記憶から全く変わらない。相変わらず風来坊だ。
「ところでアンタ、そんなしみったれた顔してどうしたんだよ?悩み事か?」
「まあ、そんなものだ」
「おーそうか。良かったら聞くぜ?」
このあっさり人を受け入れる性格も変わっていないらしい。カズヤは小さく笑い、諸々を伏せて現在の状況を話した。
「うへぇ……三角関係どころの話じゃないなぁ。しかも男かー。別に恋愛は自由だけど狙われる側となるとこう、大変だな」
「……ああ。もう帰りたい気分だ」
「でもあんまり帰りたくない気分だろ?」
「…………」
黙り込む。そうだ、自分は今から家に帰れば仁の好感度メーターを確認しなくてはならない。何なら明日からセフィロスとクラウドの調整も……。
「よし、えーと名前……」
「カズヤでいい」
「カズヤか、俺はテリー。ちょっと俺がバイトしている店に来ないか?」
「は?」
「疲れているときは全然違う世界に行ってみるのも悪くないと思うけどな。ていうか行こうぜ!」
「ちょっ、おい!?」
ぐいっと腕を引っ張られ、そのままテリーについていく形で夜の繁華街へと繰り出す。途中、何度か通行人にぶつかったが彼は気にした様子もなくどんどん進んでいく。
「なあ、どこに行くつもりなんだ」
「ん?まあ着いてからのオタノシミってやつだ。良いところには違いねぇけど」
一体どんなところに連れていかれるのだろうか。不安になりながらも、何故か足取りだけは軽くなっていく。やがて到着した場所は繁華街の隅、古いビルの3階にあるホストクラブだった。
「ここが貴様の職場か」
「職場の一つ、な。おーい店長、今いいかー!!」
“CLOSE”と看板がかけられていたドアをあっさりとテリーは開き、中に入っていった。そしてすぐに出てきたかと思うと今度は手招きしてくる。
内装はホストクラブの割に落ち着いた雰囲気だ。思っていたものとは違うが安心する。
「まだ開店時間前だから人もいないし、落ち着けるだろ?ちょっと着替えてくるからそこのソファーでコーヒー飲んで待っててくれ」
そう言ってテリーは裏に引っ込む。突っ立っているのも変だろう、とソファーに座ればフカフカの感触が返ってくる。考えればここ最近こんなゆっくりとしていなかったかもしれない。そう思うとソファーの感触だけで眠気が襲ってきた。
(……眠い)
少しだけ、少しだけだから横になろうとして肩を掴まれる。
「大丈夫かカズヤ?ちょっと疲れが溜まりすぎだと思うぞ」
「ん、だいじょ……」
その言葉は紡がれることなく途切れる。目の前にお洒落なスーツを着たテリーがいたからだ。先程までのラフな格好と違う、男でも惚れ惚れするような立ち姿。思わず見入ってしまう。
「……見惚れたか?」
「うるさい」
「アンタみたいな人も魅了できて、俺は光栄だよ」
「……ふん」
「あ、照れてる」
「誰が!!」
顔を真っ赤にして怒鳴るがテリーはクスリと笑って受け流すばかり。それが余計に腹立たしい。それに隣にドガッ、と座られると余計に落ち着かなくなる。
「結局ここに連れてきた目的はなんだ」
不安を誤魔化すように疑問をぶつければテリーはあー、とばつが悪そうな顔をして頭を掻いた。
「その、なんだ……うーん……」
「早く言え」
「何というか、放っておけなかったんだよな」
「どういうことだ?」
「カズヤ、今自分がどれだけ追い詰められてるのか自覚あるのか?目の下に隈ができていて顔色も悪い。正直見てられないぞ」
そう言って指でなぞられた頬は確かに冷たい。自分ではまったく気づかなかった。
「まあそれで、少しでもアンタが楽になれる場所があればと思って連れて来たんだ。嫌だったらゴメンな」
「まあたまになら、悪くない」
そう返せばテリーがひまわりのような眩しい笑顔を咲かせる。ああ、本当にコイツは変わらないな。前世でもそうだった。
自分よりも他人を優先して行動する性格も、誰に対しても分け隔てなく接する態度も、何もかもが懐かしい。
「じゃあこれから困ったこととか嫌なこととかあったら俺のところに来てくれ。大体何とかしてやるから!」
「その大体は力技だろうが」
「おう!」
するとポケットに入っていたスマホがバイブレーションを鳴らす。もしや仁からの連絡だろうか、と画面を見た瞬間凍りつく。
『攻略対象「テリー・ボガード」が登録されました』
「なっ……!?」
嘘だ。だって好感度及び危険度のパラメーターはテリーの近くに現れていない。なのにどうして。
「カズヤ?何かあったのか」
サポートセンターは初めに言っていた。“攻略対象は貴方に対して今日この時点、もしくは以降に大なり小なり恋愛感情 を抱いている人のみが対象となっています”と。
(まさか……)
テリーは今、自分に恋愛感情を抱いたというのか。まだ出会って数時間しか経っていないのに。信じられず、呆然としているとテリーがカズヤの顔を両手で挟み込む。
「おいどうした、やっぱり体調が悪いんじゃ」
「ひあ、なんれもない」
テリーの手から逃れようとすれば、彼は逃さないと言うかのように力を込める。痛くはないが逃げられない。
「あのな、出会って数時間の奴に言われるなんて変かもしれないけど言わせてくれ。俺に頼ってほしい。アンタの力になりたいんだ」
「っ!?」
キラキラの碧眼がカズヤの瞳を捉える。逃れようもないそれに、息が詰まった。
「……かってにしろ」
だからそう返すのが精一杯で、視線から逃れるように目を瞑る。
「……!そうか、じゃあこれからよろしくなカズヤ!」
両手が顔から離され、手を差し出される。それを握ればテリーはまたも笑顔を咲かせた。
彼の頭上に浮かぶ好感度は78、危険度は6を示していた。
【ポール√看病イベント】
今日は朝起きた時から少し肌寒い気がしていた。季節は夏と秋の間くらいで気温の変化も上がり下がりが激しい時期。
自分が肌寒いと感じるなんて珍しいこともある、と思いながら体温を測れば38.6℃。どう見ても風邪である。
(今日は何か……何もなかったか)
思い出す限り、特別な予定はなかったはず。そうと決まればとりあえず薬を飲んで、それから会社に電話をかけねば。そう決意してベッドから起き上がると足元がふらつき、視界がぐわんと揺れる。
(仁……はいなかったな)
同居している息子の仁は大学のサークル仲間と二泊三日の合宿に出掛けている。風邪をうつすことがなくてよかった。一瞬連絡しようと思ったが、そんな楽しい時間を父親の都合で台無しにするのはいただけない。
よって今日は一日安静にしていれば治るだろう。幸いにも明日は休日。ゆっくり寝ていればいい。回らないふわふわの思考で薬のあるリビングに向かおうとするが、足元がおぼつかない。それどころか目の前が真っ暗になっていく。
これは本格的にまずい。だがここで倒れたら元も子もない、暗くなった視界を捨て第六感だけで歩き出す。
「う……ぃ、ッ……た」
やっとの思いでリビングに着き、薬を飲む。すぐに治るわけではないが、時間が経てば何とかなるだろう。若干の安心感から寝室に帰るときは特に支障もなかった。だがその安心感が仇だったのか、ベッドに座り込んだ瞬間鈍器で殴られたような頭痛が走る。
「あ、あ"ぁ……!!」
声にならない悲鳴が思わず上がり、頭を手で押さえてベッドに倒れ込んだ。身体が熱いのに、震えが止まらず歯がガチガチと音を立てる。
(痛い、いたい、はやく、おさまれ……!!)
生理的な涙まで溢れてしまうあたり、かなり重症だ。このまま意識を失ってしまうのではなかろうか。いやまずG社に電話を……とスマホを手に取る。だが手がブルブル震え、画面の操作も碌にできない。それから一分後、やっと電話アプリを開きG社の番号をタップした。
プルル……と呼び出し音が鳴り響く中、早く出ろと念じ続けるとブツッ、と相手がとった音が聞こえた。
『おう!お前からかけてくるとか珍しいこともあるな。どうしたんだカズヤ?』
「……ぁ?」
電話口の向こうから聞こえてきたのはG社社員の事務的な声ではなく、カラッと陽気な声。慌てて画面を見れば“ポール・フェニックス”の文字。
『おーい、聞いてるか!?もしもーし?』
「っ、うる、さ」
間違えてしまった。しかも今現在最も聞きたくない大声と。この男、ポールは前世でも今世でもやたらと因縁があるのだ。前世はともかく今世でも絡んでいるのは嫌な意味で運命だと思ってしまう。
しかもこの男、攻略対象の一人だ。何でこんなヤツが、と何度思ったことか。
「わる、かった。まちがえた」
『ん?あ、なんだカズヤか。どうした、何かあったのか?声おかしいぞ』
急にトーンダウンする声。こいつなりに心配してくれているのだろうか。しかし今はそれが鬱陶しくて、頭がガンガンと痛む中で言葉を紡ぐ。
「きさまには、かんけい……なぃ……」
『カズヤ?カズヤ!?…………おい、返事しろ!!』
ポールの大声が聞こえてくるスマートフォンが手からズルリと抜け落ちる。それと同時に目の前が白くなった。
「何だよ……ったく」
近くのコンビニで必要最低限のものだけ買ってカズヤの住むマンションへ行く。セキュリティが厳しいところだが、幸い入っていく住民にコッソリついて行き、何とか入れた。
「も、もしもーし……」
恐らく閉められているであろう玄関をノックしてインターホンを鳴らす。反応はなし。どうしようかとドアノブを掴むとガチャ、とドアがあっさり開いた。
「セキュリティどうなってんだよ……」
ぼやきながら玄関のドアをそっと開けて中を窺うと室内は静まり返っていた。耳を澄ましてみても物音ひとつ聞こえてこない。まさかと思いつつ寝室に向かうと、そこには真っ青な顔で汗を流しながら床に倒れているカズヤが居た。
「は……?え、ちょ、大丈夫なのかよ!?」
慌てて駆け寄り、抱き起こすと酷い熱が伝わってくる。額に手を当てれば火傷するかと思うくらい熱い。
「あっつ!いやどうしたんだよお前」
「……ん、だれ、だ……?」
薄らと目を開いたカズヤは焦点の合わない瞳でポールを見つめた。普段のカズヤから想像もつかない、弱々しい瞳。
「俺だ、ポールだ!ていうか何だよこの熱。とりあえずベッドに戻るぞ!」
「……ぅ、あ」
特に抵抗もなく、されるがままのカズヤを抱きかかえてベッドに戻す。すると再び目を閉じて苦しそうに息をするだけだ。
(何でこんなになるのかね……)
ひとまず買ってきた冷却シートを額に貼り、布団をかける。これで少しは楽になってくれるといいのだが。
「俺のことわかっているよな?」
「……ぽー、る」
「よし。とりあえずスポドリ飲むか。少し起き上がれるか?」
コクリと小さく首を動かしたのを確認すると、カズヤはゆっくりと身体を起こした。スポーツドリンクを渡すと、ちびりちびりと飲み始める。いつもなら豪快に飲むさまが見られるのに、今それが見られないのはなんだか不思議な気分だった。
「薬は……」
「のんだ」
「もう飲まなくていいのか?」
「……ん」
「んじゃ寝ろ。なんかしてほしいこととかあるか?遠慮はいらないぞ」
「なら、かいしゃに、でんわしてくれ」
予想より斜め下の要求にガクッと来るが仕方ない。カズヤのスマホからG社に電話し、休む旨を伝えた。
「……おわりか?」
「おう、終わり。他にはないな?」
「……ん」
「じゃあ色々取ってくるから、寝ていろよ」
そう言って側を離れようとした瞬間、服を掴まれた。驚いて振り返ると、カズヤが眉間にシワを寄せながらも必死に何かを堪えている表情をしている。
「お?どうした、何かあったか」
「……ゃ」
「ん?」
「ゃ、だ。いか、ないで。………きらいに、なら……ない、で……」
らしくもない、どころじゃない。まるで迷子の子どものような言葉。嫌いにならないでと懇願する姿はあまりにも幼くて、頼りなさげで。そんな姿を目にして、どうして嫌えるというのか。
20年来の友人が、自分を頼ってくれている。それだけで胸の奥がじわりと温まるような感覚に陥った。
「大丈夫、大丈夫だ。お前が安心するまでここにいるさ」
「……うそは、つくなよ」
「お前なら全部お見通しだろ」
だから早く元気になれと頭を撫でてやれば、その手をぎゅっと握られた。そしてそのままカズヤは静かに眠りにつく。
まったく、世話の焼ける友人だ。そう思いながらもポールはどこか嬉しそうな顔をしていた。
胸の高鳴りは知らない。今は友人がただ安心して眠ってくれるだけでよかった。
「本当に何もやらなかったなアイツ……」
あれから一週間、万全の体調を取り戻したカズヤが安堵の声をサポートセンターに伝える。
『現在、攻略対象「ポール・フェニックス」の好感度は72、危険度が6となっています。危険度の低さが功を奏したのでしょう』
いやはや、それにしてもまさかポールが攻略対象だと知ったときの気持ちと言ったらそれはそれは微妙だったのだ。しかし今なら自信を持って言える。
「他の連中よりマシだ」
なんて。
因みにあの風邪の日の出来事をカズヤはほとんど覚えていなかった。まさか子どものようにポールへ縋ったなど、知ったら彼を殴りに行くかもしれない。
血の気の多い主人にヒヤヒヤしながらサポートセンターは今日も役目をまっとうするのだった。
【ぐだぐだ李ニキの初恋エピソード〜ポールを添えて〜】
「そういやお前の初恋ってあれだろ?カズヤだろ?」
ポールの戯言とも言い切れぬ発言に李は喉をビールで詰まらせた。ゲホゴホッと咳き込むも、目の前の男はニヤリとした笑みを浮かべたままだ。
「お、図星か〜。まあ見ていりゃわかるけど」
「耳年増には年齢が経ちすぎじゃないのか?いい加減歳を考えろ」
「おーおー、そういうこと言っちゃう?それなら俺は耳年増で構わないぜ」
この男とやはり飲むべきではなかった、と数時間前から3回ほど後悔している。無論現在4回目の記録を達成した。仕事が一段落して暇だから空いているやつを……と適当に選んだのが悪かったのだろう。これならロウの方を呼ぶべきだった。
「やはりお前は嫌いだ」
そう言い放ちグラスを一気にあおる。もう何杯目か数えていない。とにかく飲まないとやっていられない気分だ。そんな李の様子を見てか、ポールはケラケラと笑いながら自分も酒をあおった。
「しかしなんだ、あれだけアピールしてもカズヤ全然靡かないのな」
「当たり前だ、あいつはノーマルでそもそも亡くなった奥方がいる。俺に靡くわけ、わけ……」
「諦められないんだろ?」
「……」
「いいじゃねえか別に。結ばれなくても好きになる自由はあるし、案外コロッと落ちる可能性も0%じゃないんだぜ」
グラスに再び注がれるビールを見ながら、ふと考える。
初恋、だった。出で立ちも性格も何もかも李の理想と違う。そもそも兄弟喧嘩ばかりで、人の扱いが雑で、とてもじゃないが恋仲になりたいとは思えない。けれど、それでも惚れてしまったのだ。いつの間にか、一八のことを恋愛対象として意識するようになっていた。
『これからお前たちは兄弟だ』
父、とは呼びたくない義父に連れられてやって来た日本。そこで初めて会った義兄、三島一八は心底どうでもよさそうな目で李を見つめていた。それが気に食わなくて何度もちょっかいを出し、その度に返り討ちにされた。今思えば構ってくれない寂しさから起こした行動なのかもしれない。
そんな生活が続き10代後半に差し掛かった頃。初恋は些細なことから起きた。
「また平八に折檻されたのか」
「……別に、関係ないだろ」
庭園に植えられた大木の下で蹲っているといつの間にか来ていた一八がこちらを見下ろしていた。
自分が一八の当て馬だというのは既にわかっていた。一八が三島の頭首になるための踏み台、それが養子になった理由。勉強も体術も何もかも一八に追いつかない。追いつけるはずもなく、理不尽に折檻を食らうことがこの頃当たり前になっていた。
「問題集を間違えたか、それとも10人組手で負けたのか……まあどっちでもいい」
「ああそうだ。お前にとっちゃどっちでもいいだろ。俺を見下しに来たのか」
心はずっと前から荒んでいた。自分よりも強い存在が身近にいるという恐怖、そして劣等感。それらが積もりに積もって今に至る。
「別にどうでもいい。貴様が無能なのは知っている。だが関係ない、と言われる筋合いはないな」
「…………は?」
あの義兄から出た言葉は到底信じ難いほど衝撃的なものだった。
関係なくはない。それは、自分に対して少しでも興味があるということの証左だ。この義兄の心に自分が存在するということ、それだけで胸が高鳴るのを感じた。
「貴様のことは嫌いだ。だが平八はもっといけ好かん。今日だけは兄弟になってやる」
一八の懐から取り出された絆創膏が傷を負っていた頬にペタリと貼られ、そのまま頭をグシャリと撫でられた。
いつもの痛みも悔しさはなく、代わりに温かな気持ちだけが李の中に残った。
初恋の思い出に浸りながら、李はビールを煽る。
それからというもの、一八へアプローチを始めた。まずは勉強を教わるという名目で部屋へ押しかけ、食事に誘い、遊びに誘うなど今にして思うと恥ずかしいくらい必死だった。どうにかして振り向かせたくて、嫌われたくなくて、ただひたすらに努力した。
しかし未だにそれが報われることはなく、あれから30年以上が経過して今に至る。
「アラフィフが初恋に縋っている……なんて笑える話だよ」
「おっ、開き直ったか?そういうところは好きだぜ〜」
ポールの茶化しにももう反応しない。この男のペースに乗せられるとロクなことにならないのは今までの経験上よく理解している。
「最近女には飽きたとかもう若くないとか色々言っているけどさ、結局お前、カズヤのこと好きすぎるんだろ」
「…………うるさい」
「否定できないところが悲しいな」
「うぁ……うぅ……」
言葉が出ないのは敗北の宣言。認めたくない事実を言葉のナイフで突きつけられ、李は顔を両手で覆った。
「そーいやカズヤ、最近あの神羅カンパニーの社員……確か名前、あのお前と同じ銀髪の……」
「セフィロス・宝条か。話はよく聞くな。何でもイケメンな優秀社員だとか」
「そうそうそいつ。最近カズヤと一緒に出掛けたんだとさ」
ビキ、とヒビが入る音は手元のグラスからかそれとも頭の血管か。一八が、他の男と歩いていた。しかもあの神羅カンパニーの?恐らくかなり年下の男と街を?嫉妬で狂ってしまいそうになる感情を李はビールで飲み干す。
まだデートと決まったわけじゃない、焦るのはまだ……
「あとそのセフィロスの後輩とも出掛けたって話だし、最近変な友人ができたとかなんとか」
李の手の中でグラスが粉微塵に砕け散る。破片が飛び散る中、ビール瓶を掴み一気に流し込んだ。アルコールが身体に染み渡り、気分が良くなる。
だがそれも一瞬の出来事。思考が嫉妬とその他の感情でグチャグチャになり、視界がグラついた。何故今、この時期になって一八の周りに男が……!と叫びたくなる衝動を抑え、とりあえず目の前の酒を片っ端から胃に収めていく。
その様子を見てポールは苦笑いを浮かべながら追加の酒を持ってくることにした。
「ヘックション!!」
今日は暑いはずなのにくしゃみが出る。一八はティッシュを手繰り寄せ、鼻を噛んだ。
噂をされるとくしゃみが出るとはよくいうが自分なんて噂されてなんぼの立ち位置だ。なのにくしゃみが出るのはどういうことか。先日の風邪が長引いているのだろうか。
疑問に思いながらもとりあえず厚い毛布をかけ、風邪を引かないようにする。
(……そういえば今日は珍しくイベントがなかったな)
ここ最近立て続けに起きていたイベントが今日はまったくなかった。セフィロスやクラウドとデートもどきをしたり、テリーとバーで話したり、仁と喧嘩して負けたりなど色々あったのに今日は何もない。
この何もない日が続けばいいのに、と思いながら一八は眠りにつく。
『……イベント………発生』
まさか自分の計り知れぬ場所でイベントが起きているなんて、全く知る由もないのだ。
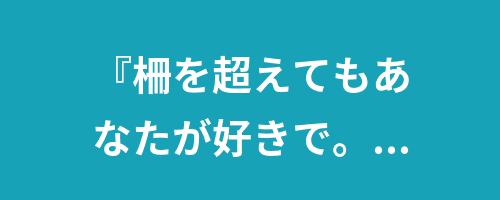 2025年04月06日 12:00〜翌11:50『柵を超えてもあなたが好きで。』クロスオーバーCPオンリークロスオーバーサークル参加受付期間0 / 72sp
2025年04月06日 12:00〜翌11:50『柵を超えてもあなたが好きで。』クロスオーバーCPオンリークロスオーバーサークル参加受付期間0 / 72sp
